「理論編第2部 ボイストレーニングを自宅で始めよう」のP.45下段~P.46のレビューです。
松澤氏の担当です。
変更履歴
2012/08/30:第10回へのリンク追加
松澤氏の担当です。
変更履歴
2012/08/30:第10回へのリンク追加
1.「のどをあけて発声するための心得」(P.45)
------- P.45より引用 Start ----------最後に、発声時にのどをあけるコツを簡単にご紹介しておきます。
------- P.45より引用 End ----------
えーと、どうして「最後に」なんですか?
「喉を開く」コツは、一番最初に書いておかないとダメでしょ!散々、喉を緊張させる方向(強い息、腹式呼吸)を強調して語った後で、「喉を開く」コツを書くんですか? 順序がまるっきり逆です。
「のどをあける」コツとして、「①あごをひいて発声する」と「②舌を平らにして発声する」の2つが松澤氏により書かれています。
「あごをひいて発声する」が、どうして「のどをあける」コツなんでしょうか?顎を引くと声帯が下がるからでしょうか? いまいち分かりません。
「②舌を平らにして発声する」には賛成です。
図1:普通の「あ」 |
図2:舌を平らにした「あ」 |
普通の日本人が普通の声の大きさで話すと、図1の状態になっています。図1は「あ」を発音したときの状態です。
「喉を開く」を実践して声を出すには、図2の状態にする必要があります。
図2では舌が平らになっているでしょ? ②舌を平らにして発声する」とは、このことです。
できれば、図1と図2のような図を付けて説明して欲しいですね。
通常、日本人は、図1のような状態で声を出していると、自分で思っていないですから。
単に「舌を平らにする」と言われると、普段の通りだと勘違いしてしまいます。
また、どうやって舌を平らにするのか、その方法が書かれていません。不完全ですね。
2.「まとめ」(P.46)
-------- P.46より引用 Start -------------いままで漫然と思い描いてきたボイストレーニングとは違っていたかもしれませんが、
「声帯を鍛えれば良い」と考えてボイストレーニングをすることはたいへん危険ですので
ご注意ください。声帯を痛めるだけです。
-------- P.46より引用 End -------------
ココまで読み進めた読者は正に「声帯を鍛えれば良い」といった声を必ず出すでしょう。
だって、息を強く出すとか、腹式呼吸とかを、さんざん強調しておいて、一方、「喉を開く」有益な秘訣が殆どかかれていないじゃないですか。
-------- P.46より引用 Start -------------
声帯は、リラックスさせてのびのびと振動させるべきです。
-------- P.46より引用 End -------------
その通りですが、本は全く正反対のことを沢山書いていますよね。
響く声の第一歩が「喉を開く」ことですが、この本にどれだけ書かれていましたか?
「喉を開く」には、喉のリラックスが必須です。
ちょっと、「理論編第2部」(P.30?P.46)の中で、緊張と弛緩に関連するアドバイスを登場した順番に並べてみましょう。
青が喉のリラックスに貢献する内容、赤が喉を緊張させる内容です。
青の太文字はリラックスの効果が大きい、赤の太文字は、緊張の度合いが激しいことを意味するものとします。
但し、記述が不十分であるために、または、抽象的であるために、読者に伝わらない場合、効果・逆効果は発生しないものと見なします。
「喉を開く」が実行できない一般の読者を想定します。
①「英語の息は、日本語の息の3?5倍は強いのです。」(P.32、 松澤氏)
②胸でひびきを感じる練習 (P.33 福島氏)
③あくび溜息法(P.34 福島氏)
④「無理に共鳴させようとしない」(P.35 福島氏)
⑤「共鳴のための脱力」(P.35 福島氏)
⑥「声を前に出す」(P.36 福島氏)
⑦「口を大きく開けすぎない。」(P.36 福島氏)
⑧「強い息を急速に吐くためには、内臓を押し上げて、横隔膜を押し上げるサポートをする必要があります。」(P.43 松澤氏)
⑨「あごをひいて発声する」(P.46 松澤氏)
⑩「舌を平らにして発声する」(P.46 松澤氏)
赤の部分が多いですね。まるで響かない声の出し方を教えられているかのようです。
今度は、既に「喉を開く」を実践し、響く声を出せる人を想定してみます。
私が、英語鼻を実践しながら、アドバイスに従って声を出してチェックしました。
①「英語の息は、日本語の息の3?5倍は強いのです。」(P.32 松澤氏)
②胸でひびきを感じる練習 (P.33 福島氏)
③あくび溜息法(P.34 福島氏)
④「無理に共鳴させようとしない」(P.35 福島氏)
⑤「共鳴のための脱力」(P.35 福島氏)
⑥「声を前に出す」(P36 福島氏)
⑦「口を大きく開けすぎない。」(P.36 福島氏)
⑧「強い息を急速に吐くためには、内臓を押し上げて、横隔膜を押し上げるサポートをする必要があります。」(P.43 松澤氏)
⑨「あごをひいて発声する」(P.46 松澤氏)
⑩「舌を平らにして発声する」(P.46 松澤氏)
本書に書かれてある腹式呼吸(=⑦)を実践すると、既に「喉を開く」が可能であり、響く声の私でさえ、響かない声になりました。
------- P.46より引用 Start -------------
上手に共鳴させられるようになるには、半年や1年は最低限必要です。
声に関しては短気は禁物です。長い目で見て、少しずつ取り組んで、良い声を獲得してください。
------- P.46より引用 End -------------
読者側の問題ではありません。
ここまでのところ、本書には、響く声を身に付けるための有効なアドバイスが殆ど書かれていません。
逆に、響かない声の秘訣はたっぷりかかれてあります。
← 第8回 第10回→
PR
1.「のどをあけて発声するための心得」(P.45)
------- P.45より引用 Start ----------最後に、発声時にのどをあけるコツを簡単にご紹介しておきます。
------- P.45より引用 End ----------
えーと、どうして「最後に」なんですか?
「喉を開く」コツは、一番最初に書いておかないとダメでしょ!散々、喉を緊張させる方向(強い息、腹式呼吸)を強調して語った後で、「喉を開く」コツを書くんですか? 順序がまるっきり逆です。
「のどをあける」コツとして、「①あごをひいて発声する」と「②舌を平らにして発声する」の2つが松澤氏により書かれています。
「あごをひいて発声する」が、どうして「のどをあける」コツなんでしょうか?顎を引くと声帯が下がるからでしょうか? いまいち分かりません。
「②舌を平らにして発声する」には賛成です。
図1:普通の「あ」 |
図2:舌を平らにした「あ」 |
普通の日本人が普通の声の大きさで話すと、図1の状態になっています。図1は「あ」を発音したときの状態です。
「喉を開く」を実践して声を出すには、図2の状態にする必要があります。
図2では舌が平らになっているでしょ? ②舌を平らにして発声する」とは、このことです。
できれば、図1と図2のような図を付けて説明して欲しいですね。
通常、日本人は、図1のような状態で声を出していると、自分で思っていないですから。
単に「舌を平らにする」と言われると、普段の通りだと勘違いしてしまいます。
また、どうやって舌を平らにするのか、その方法が書かれていません。不完全ですね。
2.「まとめ」(P.46)
-------- P.46より引用 Start -------------いままで漫然と思い描いてきたボイストレーニングとは違っていたかもしれませんが、
「声帯を鍛えれば良い」と考えてボイストレーニングをすることはたいへん危険ですので
ご注意ください。声帯を痛めるだけです。
-------- P.46より引用 End -------------
ココまで読み進めた読者は正に「声帯を鍛えれば良い」といった声を必ず出すでしょう。
だって、息を強く出すとか、腹式呼吸とかを、さんざん強調しておいて、一方、「喉を開く」有益な秘訣が殆どかかれていないじゃないですか。
-------- P.46より引用 Start -------------
声帯は、リラックスさせてのびのびと振動させるべきです。
-------- P.46より引用 End -------------
その通りですが、本は全く正反対のことを沢山書いていますよね。
響く声の第一歩が「喉を開く」ことですが、この本にどれだけ書かれていましたか?
「喉を開く」には、喉のリラックスが必須です。
ちょっと、「理論編第2部」(P.30?P.46)の中で、緊張と弛緩に関連するアドバイスを登場した順番に並べてみましょう。
青が喉のリラックスに貢献する内容、赤が喉を緊張させる内容です。
青の太文字はリラックスの効果が大きい、赤の太文字は、緊張の度合いが激しいことを意味するものとします。
但し、記述が不十分であるために、または、抽象的であるために、読者に伝わらない場合、効果・逆効果は発生しないものと見なします。
「喉を開く」が実行できない一般の読者を想定します。
①「英語の息は、日本語の息の3?5倍は強いのです。」(P.32、 松澤氏)
②胸でひびきを感じる練習 (P.33 福島氏)
③あくび溜息法(P.34 福島氏)
④「無理に共鳴させようとしない」(P.35 福島氏)
⑤「共鳴のための脱力」(P.35 福島氏)
⑥「声を前に出す」(P.36 福島氏)
⑦「口を大きく開けすぎない。」(P.36 福島氏)
⑧「強い息を急速に吐くためには、内臓を押し上げて、横隔膜を押し上げるサポートをする必要があります。」(P.43 松澤氏)
⑨「あごをひいて発声する」(P.46 松澤氏)
⑩「舌を平らにして発声する」(P.46 松澤氏)
赤の部分が多いですね。まるで響かない声の出し方を教えられているかのようです。
今度は、既に「喉を開く」を実践し、響く声を出せる人を想定してみます。
私が、英語鼻を実践しながら、アドバイスに従って声を出してチェックしました。
①「英語の息は、日本語の息の3?5倍は強いのです。」(P.32 松澤氏)
②胸でひびきを感じる練習 (P.33 福島氏)
③あくび溜息法(P.34 福島氏)
④「無理に共鳴させようとしない」(P.35 福島氏)
⑤「共鳴のための脱力」(P.35 福島氏)
⑥「声を前に出す」(P36 福島氏)
⑦「口を大きく開けすぎない。」(P.36 福島氏)
⑧「強い息を急速に吐くためには、内臓を押し上げて、横隔膜を押し上げるサポートをする必要があります。」(P.43 松澤氏)
⑨「あごをひいて発声する」(P.46 松澤氏)
⑩「舌を平らにして発声する」(P.46 松澤氏)
本書に書かれてある腹式呼吸(=⑦)を実践すると、既に「喉を開く」が可能であり、響く声の私でさえ、響かない声になりました。
------- P.46より引用 Start -------------
上手に共鳴させられるようになるには、半年や1年は最低限必要です。
声に関しては短気は禁物です。長い目で見て、少しずつ取り組んで、良い声を獲得してください。
------- P.46より引用 End -------------
読者側の問題ではありません。
ここまでのところ、本書には、響く声を身に付けるための有効なアドバイスが殆ど書かれていません。
逆に、響かない声の秘訣はたっぷりかかれてあります。
← 第8回 第10回→
ブログ制御
閲覧履歴
プロフィール
HN:
某スレの639
性別:
非公開
自己紹介:
アバター by Abi-Station
本でもネットでも他には絶対無い、英語発音の完全独自メソッド公開中!
2ちゃんねるの英語板の住人、発展途上の一英語学習者
メールを送る
当ブログについて
私の発音はコチラ
本でもネットでも他には絶対無い、英語発音の完全独自メソッド公開中!
2ちゃんねるの英語板の住人、発展途上の一英語学習者
メールを送る
当ブログについて
私の発音はコチラ
最新コメント
皆様のご意見
閲覧ランキング
(月間:2018/08/15~2018/09/15)
1.
お久しぶりです!
2.
英語鼻習得ガイダンス
11.
【英語息】第1回:理論編
12.
【キャンディ・メソッド】第21回
12.
【キャンディ・メソッド】第2回
12.
【キャンディ・メソッド】第4回
16.
英語鼻の記事一覧
16.
【キャンディ・メソッド】第3回
18.
【英語鼻:第1段階】第3回
19.
【英語喉レビュー】第42回
掲示板
【当ブログ専用掲示板】
【ハンドルネーム639が誕生した2ちゃんねるのスレッド】
【2ちゃんねるの639式スレッド】
【ハンドルネーム639が誕生した2ちゃんねるのスレッド】
【2ちゃんねるの639式スレッド】
記事カテゴリー
カレンダー
過去の記事
ブログ内検索
ロゴマーク
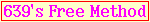

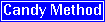

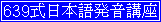
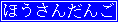

閲覧履歴画面
javascript 関数単体テスト用



