「理論編第2部 ボイストレーニングを自宅で始めよう」のP.35~P.36のレビューです。
日本人ボイストレーナーの福島氏担当部分です。
日本人ボイストレーナーの福島氏担当部分です。
1.「注意点①無理に共鳴させようとしない」
--------- P.35から引用 Start ----------共鳴のトレーニングということ自体、私は矛盾を抱きながら述べています。
なぜならひびきというのは、実はひびかすのではなく、自然とひびいてくるものだからです。
--------- P.35から引用 End ----------
本当に、その通りだと思います。
響く声の第1段階は「喉を開く」を身に付けることで初めて達成できます。
「喉を開く」を実践できない段階で、読者に共鳴させるということを意識させると、誤った方向へ進んでしまうんです。
想像してください。「喉を開く」を実践できない人が、共鳴させようとすることを何をするかを。素人がオペラ歌手の声を真似るときのことを。
- 下顎を大きく口腔を大きくする。
- 声を響かせようとして大きな声を出す。
- 力んでしまう。
---------- P.31から引用 Start ---------------
強くひびく声は、身体全体を共鳴させることを意識すると出るようになります。
---------- P.31から引用 End ---------------
松澤氏が書かれた↑は、全くナンセンスなんですよ。
「喉を開く」には、喉をリラックスさせることが必須。共鳴させることを意識するということは、体を緊張させることです。
現在のところ、松澤氏は最初の段階から、息の強さを強調したり、共鳴させることを意識させようとしたり、松澤氏は、体を緊張させることばかり書かれています。
松澤氏が書いていることは、響かない声を読者に強制させようとしていると思えるほどですよ。
2.「注意点②声の芯と、共鳴のための脱力」
--------- P.36から引用 Start ----------声を強くひびかせながら、余計なところには力を入れないという感覚を
体得してください。2倍の力で2倍ひびかせるのではなく、半分の力でも
ひびきを失わないようにするイメージです。
--------- P.36から引用 End ----------
全くその通りだと思います。共著者の松澤氏に言って下さい。
響く声の第1段階は「喉を開く」ことができるようになることです。
それには、リラックス・脱力こそが大事です。「注意点」として書くのではなく、メインのアドバイスとして書くべきではありませんか?
3.「注意点④声を前に出す」
これについては、少し説明が必要なようです。
図1:日本人が普通に声を出した状態 |
図2:日本人が口を大きく開けて声を出した状態 |
図3:欧米人が普通に声を出した状態

普通の日本人が声を出すと、図1の状態です。大きな声を出したり、口を大きく開けて声を出すと、図2の状態になります。響く声の目標は欧米人の状態、図3です。
日本人が習得する段階は、
①図1の状態から、口を大きく開けなくても図2の状態にする。つまり、舌を脱力し、舌を平らにする。
②図2の状態から図3の状態にする。つまり、喉、口内、舌、つまり、首から上を脱力する。です。
図1?図3の青丸で囲まれた箇所を見て下さい。これが軟口蓋です。図1と図2では完全に上がりきっています。図3では上に上がっていません。
「喉を開く」を実践すると、声を出しても軟口蓋が上がりきらないんです。ここまではいいですか?
-------- P.36から引用 Start ---------
声を前に出すとは、響きを前に出すということです。
-------- P.36から引用 End ---------
これは、既に「喉が開く」を実践可能な人に対しては、軟口蓋を下がりすぎないようにする有効なアドバイスです。「喉を開く」を身に付けたばかりの状態では、軟口蓋が下がりすぎて、言葉としての明瞭さが欠け、曇った声の響きになるからです。このアドバイスは、それを改善するものでしょう。
しかし、このアドバイスは、既に「喉を開く」が完全に実践可能な人向けのアドバイスです。
「喉を開く」を実践できない人が、このアドバイスを読むとどういうことが起きると思いますか?
- 声帯・喉仏が上がり、のどが緊張する。
- 舌の奥が盛り上がる。
- 首に力が入る
何故なら、「息を吐く」というイメージそのものが、「喉を閉じる」作用と、軟口蓋を上げるきってしまう作用があるからです。
日本では、役者やアナウンサーが明瞭な日本語を話すコツとして、「声と息を口から水平にまっすぐ出す」を実践します。このコツは、日本語のボイストレーニングを受けたことのある人にとっては常識です。一般の人はご存じないかも知れませんが、このコツを我々は無自覚に実践しているのです。それを明文化して、今一度、再確認させるのが、このコツの文言です。
「息を吐く」イメージ → 日本語の発声方法 → 「喉を閉じる」、「舌の奥が盛り上がる」 、です。
P.36の「声を前に出す」というアドバイスは、「喉を開く」ことができない人に言ってはダメなのです。
このアドバイスをするのなら、既に「喉を開く」ことが実践できて、体に馴染んだ人ではないとダメなんです。
この本のレビューで再三、私が言っていることですが、どうして、読者の進行具合によってレベル分けしないんですか?
アドバイスは万人に効く物じゃありません。
アドバイスをする側は、読者がそのアドバイスを受けるにふさわしい状態かどうかを、絶対に見極める必要があるのです。
← 第6回 第8回 →
PR
1.「注意点①無理に共鳴させようとしない」
--------- P.35から引用 Start ----------共鳴のトレーニングということ自体、私は矛盾を抱きながら述べています。
なぜならひびきというのは、実はひびかすのではなく、自然とひびいてくるものだからです。
--------- P.35から引用 End ----------
本当に、その通りだと思います。
響く声の第1段階は「喉を開く」を身に付けることで初めて達成できます。
「喉を開く」を実践できない段階で、読者に共鳴させるということを意識させると、誤った方向へ進んでしまうんです。
想像してください。「喉を開く」を実践できない人が、共鳴させようとすることを何をするかを。素人がオペラ歌手の声を真似るときのことを。
- 下顎を大きく口腔を大きくする。
- 声を響かせようとして大きな声を出す。
- 力んでしまう。
---------- P.31から引用 Start ---------------
強くひびく声は、身体全体を共鳴させることを意識すると出るようになります。
---------- P.31から引用 End ---------------
松澤氏が書かれた↑は、全くナンセンスなんですよ。
「喉を開く」には、喉をリラックスさせることが必須。共鳴させることを意識するということは、体を緊張させることです。
現在のところ、松澤氏は最初の段階から、息の強さを強調したり、共鳴させることを意識させようとしたり、松澤氏は、体を緊張させることばかり書かれています。
松澤氏が書いていることは、響かない声を読者に強制させようとしていると思えるほどですよ。
2.「注意点②声の芯と、共鳴のための脱力」
--------- P.36から引用 Start ----------声を強くひびかせながら、余計なところには力を入れないという感覚を
体得してください。2倍の力で2倍ひびかせるのではなく、半分の力でも
ひびきを失わないようにするイメージです。
--------- P.36から引用 End ----------
全くその通りだと思います。共著者の松澤氏に言って下さい。
響く声の第1段階は「喉を開く」ことができるようになることです。
それには、リラックス・脱力こそが大事です。「注意点」として書くのではなく、メインのアドバイスとして書くべきではありませんか?
3.「注意点④声を前に出す」
これについては、少し説明が必要なようです。
図1:日本人が普通に声を出した状態 |
図2:日本人が口を大きく開けて声を出した状態 |
図3:欧米人が普通に声を出した状態

普通の日本人が声を出すと、図1の状態です。大きな声を出したり、口を大きく開けて声を出すと、図2の状態になります。響く声の目標は欧米人の状態、図3です。
日本人が習得する段階は、
①図1の状態から、口を大きく開けなくても図2の状態にする。つまり、舌を脱力し、舌を平らにする。
②図2の状態から図3の状態にする。つまり、喉、口内、舌、つまり、首から上を脱力する。です。
図1?図3の青丸で囲まれた箇所を見て下さい。これが軟口蓋です。図1と図2では完全に上がりきっています。図3では上に上がっていません。
「喉を開く」を実践すると、声を出しても軟口蓋が上がりきらないんです。ここまではいいですか?
-------- P.36から引用 Start ---------
声を前に出すとは、響きを前に出すということです。
-------- P.36から引用 End ---------
これは、既に「喉が開く」を実践可能な人に対しては、軟口蓋を下がりすぎないようにする有効なアドバイスです。「喉を開く」を身に付けたばかりの状態では、軟口蓋が下がりすぎて、言葉としての明瞭さが欠け、曇った声の響きになるからです。このアドバイスは、それを改善するものでしょう。
しかし、このアドバイスは、既に「喉を開く」が完全に実践可能な人向けのアドバイスです。
「喉を開く」を実践できない人が、このアドバイスを読むとどういうことが起きると思いますか?
- 声帯・喉仏が上がり、のどが緊張する。
- 舌の奥が盛り上がる。
- 首に力が入る
何故なら、「息を吐く」というイメージそのものが、「喉を閉じる」作用と、軟口蓋を上げるきってしまう作用があるからです。
日本では、役者やアナウンサーが明瞭な日本語を話すコツとして、「声と息を口から水平にまっすぐ出す」を実践します。このコツは、日本語のボイストレーニングを受けたことのある人にとっては常識です。一般の人はご存じないかも知れませんが、このコツを我々は無自覚に実践しているのです。それを明文化して、今一度、再確認させるのが、このコツの文言です。
「息を吐く」イメージ → 日本語の発声方法 → 「喉を閉じる」、「舌の奥が盛り上がる」 、です。
P.36の「声を前に出す」というアドバイスは、「喉を開く」ことができない人に言ってはダメなのです。
このアドバイスをするのなら、既に「喉を開く」ことが実践できて、体に馴染んだ人ではないとダメなんです。
この本のレビューで再三、私が言っていることですが、どうして、読者の進行具合によってレベル分けしないんですか?
アドバイスは万人に効く物じゃありません。
アドバイスをする側は、読者がそのアドバイスを受けるにふさわしい状態かどうかを、絶対に見極める必要があるのです。
← 第6回 第8回 →
ブログ制御
閲覧履歴
プロフィール
HN:
某スレの639
性別:
非公開
自己紹介:
アバター by Abi-Station
本でもネットでも他には絶対無い、英語発音の完全独自メソッド公開中!
2ちゃんねるの英語板の住人、発展途上の一英語学習者
メールを送る
当ブログについて
私の発音はコチラ
本でもネットでも他には絶対無い、英語発音の完全独自メソッド公開中!
2ちゃんねるの英語板の住人、発展途上の一英語学習者
メールを送る
当ブログについて
私の発音はコチラ
最新コメント
皆様のご意見
閲覧ランキング
(月間:2018/08/15~2018/09/15)
1.
お久しぶりです!
2.
英語鼻習得ガイダンス
11.
【英語息】第1回:理論編
12.
【キャンディ・メソッド】第21回
12.
【キャンディ・メソッド】第2回
12.
【キャンディ・メソッド】第4回
16.
英語鼻の記事一覧
16.
【キャンディ・メソッド】第3回
18.
【英語鼻:第1段階】第3回
19.
【英語喉レビュー】第42回
掲示板
【当ブログ専用掲示板】
【ハンドルネーム639が誕生した2ちゃんねるのスレッド】
【2ちゃんねるの639式スレッド】
【ハンドルネーム639が誕生した2ちゃんねるのスレッド】
【2ちゃんねるの639式スレッド】
記事カテゴリー
カレンダー
過去の記事
ブログ内検索
ロゴマーク
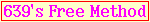

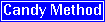

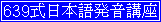
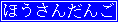

閲覧履歴画面
javascript 関数単体テスト用



