「理論編第2部 ボイストレーニングを自宅で始めよう」のP.32下段~P.38のレビューです。
日本人ボイストレーナーの福島氏担当部分です。
日本人ボイストレーナーの福島氏担当部分です。
------------ P.32から引用 Start -------------
ここで、強くひびく声が出る原理と練習方法について、私(福島)がお話ししていきましょう。
------------ P.32から引用 End -------------
ちょっと待った!! 練習方法ってなんですか?
このページは「理論編第2部」ですよ。理論編です。実践編ではないですよ!
どうして、福島氏による実践トレーニングが理論編に書かれてあるんですか!?
P.32~P.38の福島氏担当部分のタイトルを抜き出してみました。
①声を体に共鳴させる練習
②胸でひびきを感じる(胸部共鳴)練習
③さらに胸にひびかせる練習
④口内での共鳴ポイントを知る練習
⑤鼻の共鳴の練習
⑥母音のひびきを統一する練習
注意点①無理に共鳴させようとしない
注意点②声の芯と、共鳴のための脱力
注意点③小さな声、弱い声でもひびきをキープする
注意点④声を前に出す
注意点⑤口を大きく開けすぎない
注意点⑥硬い声になっていないかのチェック
タイトルを見る限り、たった7ページに、声楽の学問体系の中の、発声の基本トレーニングが網羅されています。本来なら、この7ページ分で1冊の本がかけてしまう内容です。
なんなんですか、これは! どうして、これを「実践編」へ統合しないんですか?
前から順番に読み進めている読者は、もう~、わけが分からない状態になりますよ。
先の回で、私が述べたように、著者、編集担当者は、読者の習得状態を全く考慮していないでしょ?
読者が習得する様子を、ちゃんとシミュレーションしてないでしょ?
これがレビュー第2回にて、私が述べた「船頭多くして船、山に上る」のことです。
本は、「理論編」と「実践編」に分かれていますが、この分け方は嘘です。
自称「理論編」には、
・松澤氏による理論と実践方法
・福島氏による理論と実践方法
が書かれてあります。
自称「実践編」には、
・アメリカ人のボイストレーナー、オコナー氏による実践方法
・福島氏による「補足」というタイトルの、実践方法
が書かれてあります。
しかも、3氏の担当分野の守備範囲が明確に分かれているのではなく、3氏で守備範囲が重複しています。
なんなんですか、これは?
こんな状態になるのなら、「共著」ではなく、3人がそれぞれ、本を書けばいいじゃないですか?
複数人数で共著する場合、同じテーマについて、それぞれの著者が書いたりしないでしょ? 役割分担をしっかり行い、章間に矛盾が無いか、後の章の内容が前の章を継承しているか、しっかり管理して本を書くものですよね?
この本の編集・管理は、どうなっているんですか?
また、言ってしまいますが、この本の様に酷い構成の本を見たことがありません。
次回は、「理論編第2部 ボイストレーニングを自宅で始めよう」のP.32下段~P.38の内、気になった箇所について、レビューします。
← 第4回 第6回 →
ここで、強くひびく声が出る原理と練習方法について、私(福島)がお話ししていきましょう。
------------ P.32から引用 End -------------
ちょっと待った!! 練習方法ってなんですか?
このページは「理論編第2部」ですよ。理論編です。実践編ではないですよ!
どうして、福島氏による実践トレーニングが理論編に書かれてあるんですか!?
P.32~P.38の福島氏担当部分のタイトルを抜き出してみました。
①声を体に共鳴させる練習
②胸でひびきを感じる(胸部共鳴)練習
③さらに胸にひびかせる練習
④口内での共鳴ポイントを知る練習
⑤鼻の共鳴の練習
⑥母音のひびきを統一する練習
注意点①無理に共鳴させようとしない
注意点②声の芯と、共鳴のための脱力
注意点③小さな声、弱い声でもひびきをキープする
注意点④声を前に出す
注意点⑤口を大きく開けすぎない
注意点⑥硬い声になっていないかのチェック
タイトルを見る限り、たった7ページに、声楽の学問体系の中の、発声の基本トレーニングが網羅されています。本来なら、この7ページ分で1冊の本がかけてしまう内容です。
なんなんですか、これは! どうして、これを「実践編」へ統合しないんですか?
前から順番に読み進めている読者は、もう~、わけが分からない状態になりますよ。
先の回で、私が述べたように、著者、編集担当者は、読者の習得状態を全く考慮していないでしょ?
読者が習得する様子を、ちゃんとシミュレーションしてないでしょ?
これがレビュー第2回にて、私が述べた「船頭多くして船、山に上る」のことです。
本は、「理論編」と「実践編」に分かれていますが、この分け方は嘘です。
自称「理論編」には、
・松澤氏による理論と実践方法
・福島氏による理論と実践方法
が書かれてあります。
自称「実践編」には、
・アメリカ人のボイストレーナー、オコナー氏による実践方法
・福島氏による「補足」というタイトルの、実践方法
が書かれてあります。
しかも、3氏の担当分野の守備範囲が明確に分かれているのではなく、3氏で守備範囲が重複しています。
なんなんですか、これは?
こんな状態になるのなら、「共著」ではなく、3人がそれぞれ、本を書けばいいじゃないですか?
複数人数で共著する場合、同じテーマについて、それぞれの著者が書いたりしないでしょ? 役割分担をしっかり行い、章間に矛盾が無いか、後の章の内容が前の章を継承しているか、しっかり管理して本を書くものですよね?
この本の編集・管理は、どうなっているんですか?
また、言ってしまいますが、この本の様に酷い構成の本を見たことがありません。
次回は、「理論編第2部 ボイストレーニングを自宅で始めよう」のP.32下段~P.38の内、気になった箇所について、レビューします。
← 第4回 第6回 →
PR
------------ P.32から引用 Start -------------
ここで、強くひびく声が出る原理と練習方法について、私(福島)がお話ししていきましょう。
------------ P.32から引用 End -------------
ちょっと待った!! 練習方法ってなんですか?
このページは「理論編第2部」ですよ。理論編です。実践編ではないですよ!
どうして、福島氏による実践トレーニングが理論編に書かれてあるんですか!?
P.32~P.38の福島氏担当部分のタイトルを抜き出してみました。
①声を体に共鳴させる練習
②胸でひびきを感じる(胸部共鳴)練習
③さらに胸にひびかせる練習
④口内での共鳴ポイントを知る練習
⑤鼻の共鳴の練習
⑥母音のひびきを統一する練習
注意点①無理に共鳴させようとしない
注意点②声の芯と、共鳴のための脱力
注意点③小さな声、弱い声でもひびきをキープする
注意点④声を前に出す
注意点⑤口を大きく開けすぎない
注意点⑥硬い声になっていないかのチェック
タイトルを見る限り、たった7ページに、声楽の学問体系の中の、発声の基本トレーニングが網羅されています。本来なら、この7ページ分で1冊の本がかけてしまう内容です。
なんなんですか、これは! どうして、これを「実践編」へ統合しないんですか?
前から順番に読み進めている読者は、もう~、わけが分からない状態になりますよ。
先の回で、私が述べたように、著者、編集担当者は、読者の習得状態を全く考慮していないでしょ?
読者が習得する様子を、ちゃんとシミュレーションしてないでしょ?
これがレビュー第2回にて、私が述べた「船頭多くして船、山に上る」のことです。
本は、「理論編」と「実践編」に分かれていますが、この分け方は嘘です。
自称「理論編」には、
・松澤氏による理論と実践方法
・福島氏による理論と実践方法
が書かれてあります。
自称「実践編」には、
・アメリカ人のボイストレーナー、オコナー氏による実践方法
・福島氏による「補足」というタイトルの、実践方法
が書かれてあります。
しかも、3氏の担当分野の守備範囲が明確に分かれているのではなく、3氏で守備範囲が重複しています。
なんなんですか、これは?
こんな状態になるのなら、「共著」ではなく、3人がそれぞれ、本を書けばいいじゃないですか?
複数人数で共著する場合、同じテーマについて、それぞれの著者が書いたりしないでしょ? 役割分担をしっかり行い、章間に矛盾が無いか、後の章の内容が前の章を継承しているか、しっかり管理して本を書くものですよね?
この本の編集・管理は、どうなっているんですか?
また、言ってしまいますが、この本の様に酷い構成の本を見たことがありません。
次回は、「理論編第2部 ボイストレーニングを自宅で始めよう」のP.32下段~P.38の内、気になった箇所について、レビューします。
← 第4回 第6回 →
ここで、強くひびく声が出る原理と練習方法について、私(福島)がお話ししていきましょう。
------------ P.32から引用 End -------------
ちょっと待った!! 練習方法ってなんですか?
このページは「理論編第2部」ですよ。理論編です。実践編ではないですよ!
どうして、福島氏による実践トレーニングが理論編に書かれてあるんですか!?
P.32~P.38の福島氏担当部分のタイトルを抜き出してみました。
①声を体に共鳴させる練習
②胸でひびきを感じる(胸部共鳴)練習
③さらに胸にひびかせる練習
④口内での共鳴ポイントを知る練習
⑤鼻の共鳴の練習
⑥母音のひびきを統一する練習
注意点①無理に共鳴させようとしない
注意点②声の芯と、共鳴のための脱力
注意点③小さな声、弱い声でもひびきをキープする
注意点④声を前に出す
注意点⑤口を大きく開けすぎない
注意点⑥硬い声になっていないかのチェック
タイトルを見る限り、たった7ページに、声楽の学問体系の中の、発声の基本トレーニングが網羅されています。本来なら、この7ページ分で1冊の本がかけてしまう内容です。
なんなんですか、これは! どうして、これを「実践編」へ統合しないんですか?
前から順番に読み進めている読者は、もう~、わけが分からない状態になりますよ。
先の回で、私が述べたように、著者、編集担当者は、読者の習得状態を全く考慮していないでしょ?
読者が習得する様子を、ちゃんとシミュレーションしてないでしょ?
これがレビュー第2回にて、私が述べた「船頭多くして船、山に上る」のことです。
本は、「理論編」と「実践編」に分かれていますが、この分け方は嘘です。
自称「理論編」には、
・松澤氏による理論と実践方法
・福島氏による理論と実践方法
が書かれてあります。
自称「実践編」には、
・アメリカ人のボイストレーナー、オコナー氏による実践方法
・福島氏による「補足」というタイトルの、実践方法
が書かれてあります。
しかも、3氏の担当分野の守備範囲が明確に分かれているのではなく、3氏で守備範囲が重複しています。
なんなんですか、これは?
こんな状態になるのなら、「共著」ではなく、3人がそれぞれ、本を書けばいいじゃないですか?
複数人数で共著する場合、同じテーマについて、それぞれの著者が書いたりしないでしょ? 役割分担をしっかり行い、章間に矛盾が無いか、後の章の内容が前の章を継承しているか、しっかり管理して本を書くものですよね?
この本の編集・管理は、どうなっているんですか?
また、言ってしまいますが、この本の様に酷い構成の本を見たことがありません。
次回は、「理論編第2部 ボイストレーニングを自宅で始めよう」のP.32下段~P.38の内、気になった箇所について、レビューします。
← 第4回 第6回 →
ブログ制御
閲覧履歴
プロフィール
HN:
某スレの639
性別:
非公開
自己紹介:
アバター by Abi-Station
本でもネットでも他には絶対無い、英語発音の完全独自メソッド公開中!
2ちゃんねるの英語板の住人、発展途上の一英語学習者
メールを送る
当ブログについて
私の発音はコチラ
本でもネットでも他には絶対無い、英語発音の完全独自メソッド公開中!
2ちゃんねるの英語板の住人、発展途上の一英語学習者
メールを送る
当ブログについて
私の発音はコチラ
最新コメント
皆様のご意見
閲覧ランキング
(月間:2018/08/15~2018/09/15)
1.
お久しぶりです!
2.
英語鼻習得ガイダンス
11.
【英語息】第1回:理論編
12.
【キャンディ・メソッド】第21回
12.
【キャンディ・メソッド】第2回
12.
【キャンディ・メソッド】第4回
16.
英語鼻の記事一覧
16.
【キャンディ・メソッド】第3回
18.
【英語鼻:第1段階】第3回
19.
【英語喉レビュー】第42回
掲示板
【当ブログ専用掲示板】
【ハンドルネーム639が誕生した2ちゃんねるのスレッド】
【2ちゃんねるの639式スレッド】
【ハンドルネーム639が誕生した2ちゃんねるのスレッド】
【2ちゃんねるの639式スレッド】
記事カテゴリー
カレンダー
過去の記事
ブログ内検索
ロゴマーク
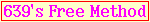

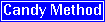

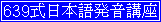
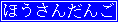

閲覧履歴画面
javascript 関数単体テスト用



